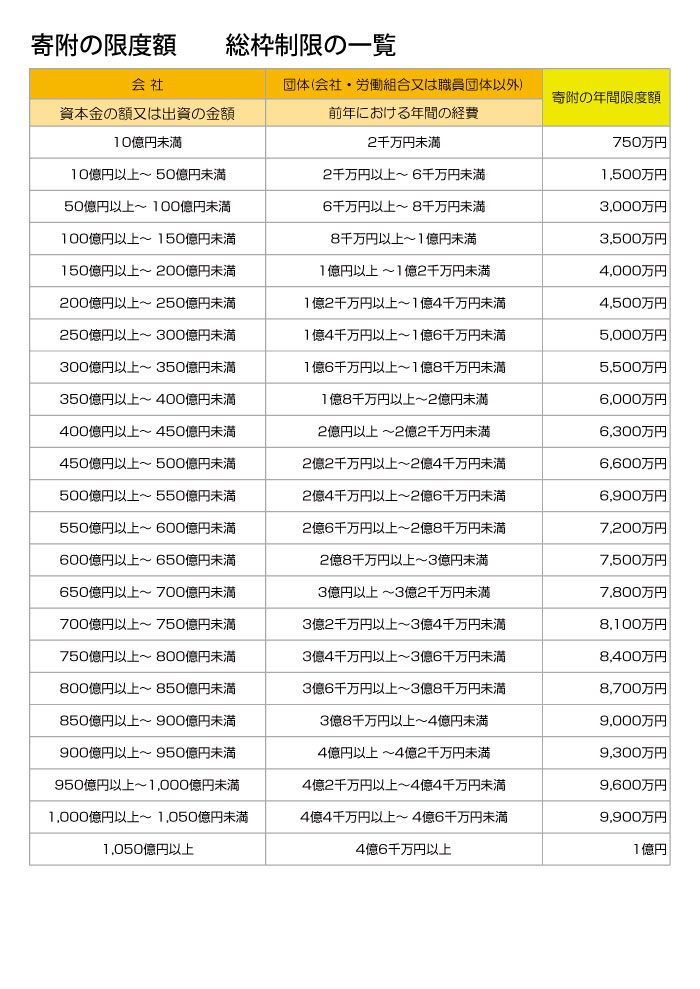1. 事故原因の究明・対応の検証
福島第一原発事故後、国会、政府、民間(一般財団法人・日本再建イニシアティブ)、東京電力の4つの事故調査委員会が立ち上げられ、それぞれが事故原因の究明や事故時の対応の検証、さらに提言・課題などの検討結果を報告している。いずれの委員会も事故の1年後の2012年までに報告書をまとめたが、事故原因の解明・特定までには至っていない。これは、何より重要なことであるが、福島第一原発の環境が悪く詳細な現地調査ができなかったこと、再現実験による事故の検証が行われなかったことが理由として挙げられている。
これを受けて、国会、政府両事故調査委員会は、継続調査の必要性を提言している。すなわち、国会事故調査委員会は、民間専門家中心の第三者機関を国会に設置し、廃炉の道筋や使用済み核燃料問題等も含めた調査審議を継続すること、政府事故調査委員会は、関係機関がそれぞれの立場で調査・検証を続けつつ、国が主導的に事故原因の解明・被害の全容把握に努めることを求めている。
しかし、現在に至るまで、これらの提言に従って国や東京電力などの関係機関が、真剣にフォローアップをしている姿は見られない。国会事故調査委員会が指摘した「依然として事故は収束しておらず、被害も継続している」という言葉をどう受け止めているのであろうか。
ちなみに、東京電力事故調査委員会は、規制に沿 って対策を進めてきたが、今般の津波は想定を大きく超えるもの、つまり「想定外」だったとして、予想通り報告書では自己保身を貫いた。
大津波に対する対策が不備であったことによる全電源喪失が事故の主因とするのが、大方の見解であった。ただし、国会事故調査委員会の見解では、「自然災害ではなく明らかに人災だ」と断定した上で、原因は津波だけでなく「安全上重要な機器の地震による損傷の可能性も否定できない」とした。
本来、国が行うべき作業を新潟県が独自に「三つの検証」の一つとして「新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」において事故原因の検証を行っている。昨年10月、まとめられた報告書では、「重要機器が津波だけでなく、地震の揺れで損傷した可能性がある」と指摘した。
なお、申し訳程度だが、2013年から原子力規制委員会の「東京電力福島第一原子力発電所における事故分析に係る検討会」が検討を行っている。これにより、3号機原子炉建屋内に高線量区域が新たに発見され、最近では、ベント用配管が、1,2号機共用排気筒の根元までにしか達していなかったことが判明するなどした。しかし、「地震による安全上重要な機器の破損」は、未だに「可能性がある」の域を出ることはなく確定していない。
※元東電幹部3名を被告人として争われている刑事裁判
争点となっている大津波の「予見可能性」について、2008年原子力設備管理部長だった吉田昌郎氏(故人)は、東電子会社が算出した津波高さ15.7メートルとの結果を、当時の常務取締役原子力・立地本部副本部長武藤栄被告人に報告している。結果、大津波対策は先延ばしになったのだが、彼は賢明で直感の働く男である。算出された値を見た瞬間に信憑性があると深刻に考えたのだろう。だから、自らは判断できず上司の判断を仰いだのだと思う。反対に、いい加減なデータならば自分のところで止めて上に報告するはずがない。彼にこそ、絶対に法廷で証人として真実を語って欲しかっただけに残念でならない。
また同年、山下和彦新潟県中越沖地震対策センター所長が「御前会議」(役員らが出席)で、政府の地震調査研究推進本部の長期評価に基づいて津波対策を実施する方針を被告人らに説明し、会社としてその方針が了承されたと法廷で供述(書面)している。が、一審では裁判長は否定した。山下氏は健康上の理由で出廷できない状態だったが、退社しているので今後は法廷で口頭陳述することを望む。
2.損害賠償
東京電力のホームページには、「福島復興への責任を果たすために『福島の復興なくして東京電力の改革、再生はあり得ない』との決意の下、事故の責任を全うすると共に、福島の生活環境と産業の復興を全力で進めてまいります」、また「原子力損害賠償について、被害を受けられた方々に早期に生活再建の第一歩を踏み出していただくため、社員ひとりひとり、真摯にご対応させていただきます」、さらに除染については「避難を余儀なくされている方々の一日も早い帰還に向けて、国・自治体の除染活動への社員派遣や技術支援などを行っています」と掲げられていた。
現在は、損害賠償の迅速かつ適切な実施のための方策(「3つの誓い」)
① 最後の一人まで賠償貫徹
② 迅速かつきめ細やかな賠償の徹底
③ 和解仲介案の尊重
となっている。
(1)被害者救済は掛け声だけ
賠償請求では、請求書の枚数が膨大なことが問題となり、請求書の記載の些細な不備、たとえば住所に「福島県」や「双葉郡」がないことで書類が無効になる実態が明らかになった。また、電話の応対は東京電力社員ではなく派遣会社が行うとか、業務効率が悪いなど多くの被害者を無視した行動が話題になった。
その中でも親身になって被害者への対応した東京電力社員もいた。しかし、それをよしとしない上司とのトラブルで心身に変調を来たして、会社を退職する羽目になってしまった。彼は、労災申請を出したが却下され、今も東京電力と闘っている。
東京電力は、お役所並みの縦割り組織であり、原子力部門以外の社員の多くは「原子力がヘマをしたばかりに、何で真面目にやっている我々が割を食うのか」と考えているだろう。したがって、「原子力が起こした事故の後始末は原子力がやれ」となり、賠償業務を任された社員が親身になって仕事をする気になれないのは無理もない。
こういった被害者に寄り添わない損害賠償がまかり通ってしまうのは、東京電力の責任だけではない。もとより、国策として原発を推進して来た政府が損害賠償業務を行うべきところを、「矢面に立ちたくない」との理由で、破綻状態の東京電力を延命させ肩代わりさせているところにも問題がある。
(2)被害者が分断される現実
損害賠償は、政府が定めた避難区域に従って行われている。この区域割りは、所詮地図上に引かれた線であり、その「線引き」によって被害者は区別あるいは差別されている。線の内と外では賠償金額に大きな差があるのだ。このため、被害者の方々の間には不公平感が生じ、対立や分断が起きているという。
被害者の対立・分断は、原発事故のみならずさまざまな損害賠償を伴う公害、事件・事故などに共通して存在するが、それが被害者の切り捨てにつながることも否定できない。福島県では友人や家族といった身近な存在の間でも対立・分断が生まれ、精神的な不安や苦痛にあえいでいる人も多いと聞いている。避難している被害者と地元にとどまっている被害者との間に相違があり、同じ避難している人でも、強制か自主(避難)かによって待遇は大きく変わってくる。
(3)誰のための避難指示解除なのか
そんな被害者の悩みをよそに、政府は国道6号線、常磐道、JR常磐線などの交通インフラを復旧するとともに、避難指示解除準備区域と居住制限区域の避難指示を次々と解除している。2017年3月、帰還困難区域を除いて、すべての避難指示が解除された。年間追加被曝線量20ミリシーベルト相当以下になることが目安とされている。
しかし、これらはあまりにも拙速なやり方である。まず、年間20ミリシーベルトという数字に疑問があるが、「復興」のイメージ付けと補償負担の削減を睨んだ施策に違いない。避難解除と補償削減は、あくまでワンセットなのだ。なお、福島第一原発は運転していないものの廃炉作業中であり、「緊急事態」が発生する可能性はゼロではない。その場合に備えた避難計画が、避難解除された自治体では策定されていないことが明らかとなっている。
その仕上げが「復興五輪」なのだろう。どこが復興なのか。復旧さえほど遠い状態である。10市町村の旧避難区域での居住率(住民登録者数に占める現居住者の割合)は、31.8%、浪江、富岡両町の居住率は10%台にとどまり、とりわけ帰還が進んでいない。「安全神話」が崩壊したと思ったら、いつの間にか「復興神話」が跋扈(ばっこ)している。
(4)切り捨てられた自主避難者
一方、福島県は災害救助法に基づき、東日本大震災と原発事故で避難した県民を対象に仮設や借り上げの住宅提供を開始した。しかし、2017年3月末で避難区域外からの避難いわゆる「自主避難者」への提供が終了した。対象者は報道によれば約2万6000人といわれている。「自主避難」している人達の中には、経済的に困窮して、いやでも「帰還」せざるを得ない人もいるだろう。2017年3月前橋地方裁判所の判決で「自主避難」の合理性が認められた。この判断に照らせば、支援を打ち切った上で、その後の家賃を訴訟の場に持ち込んでまで請求する福島県の措置は理不尽と言うほかはない。
こういった措置により、事故による避難者数は見かけ上激減した。現在、避難している人がどの程度いるのか、正確な数字は国も地方自治体も把握していないであろう。
(5)原子力損害賠償紛争解決センターと福島原発訴訟
損害賠償にかかわる紛争を円滑、迅速、かつ公正に解決することを目的として、2011年8月、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会のもとに原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR:Alternative Dispute Resolution)が設置された。
だが、ADRが示した和解案を東京電力が拒否するケースが多発した。直近のデータでは2021年2月25日現在で26644件の申し立てがあり、そのうち20641件が和解している。和解が不調に終わり裁判に発展するケースも含め、福島第一原発事故の避難者らが東京電力や国を相手取り慰謝料など損害賠償を求める集団訴訟は、全国で約30件ある。このうち3件について高裁判決が出されているが、国と東京電力の責任を認めたのは2件である(「福島生業訴訟」と「千葉集団訴訟」)。裁判所の判断が分かれるなか、今後も注視していく必要がある。
(6)損害賠償支払額
東京電力の賠償支払額の累計(除染費用を含む)は、2021年2月現在で9兆7338億円に上り、来年度にも10兆円を超える見通しだ。この資金は、国から原子力損害賠償・廃炉等支援機構を通じて交付された。上限は13兆5000億円だが、賠償金支払いは裁判所賠償額上乗せ判決等により増加傾向にあり、これに達する可能性もある。
交付金は無利子で、東京電力及び新電力を含む電力会社が払う負担金で返済されており、多くは電気料金に転嫁されて私たちが負担している。ただ、東京電力は柏崎刈羽原発の再稼働で見込まれる収入を返済に充てる信じ難い計画を立てている。また、除染費用は東京電力の株式売却益で賄うとしているが、この株高のご時世にありながら、現在の株価が4倍に上がらなければ実現しない。
なお、福島第一原発事故に係る消滅時効は10年であり、3月11日でちょうど10年となる。東京電力は、「『最後の一人まで賠償貫徹』という考え方のもと、消滅時効に関して柔軟な対応をする」としているが、果たしてその決意は実行されるのだろうか。
3.廃炉作業
通常、廃炉は、使用済燃料を搬出し、系統除染(配管内などに付着している放射性物質の除去)や、放射能を減衰させるため安全貯蔵を経て、建屋内部の解体・撤去、建屋の解体・撤去、最終的に廃棄物の処理・処分をする流れで行われる。この工程は、20~30年を要するとされている。
しかし、福島第一原発の廃炉は勝手が違う。何しろ、炉心が溶融しているのだ。東京電力は、福島第一廃炉推進カンパニーを設置するなど政府と協力して、これに取り組む姿勢を見せる。政府の廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議は、政府と東京電力が原子力損害賠償・廃炉等支援機構の技術的な検討も踏まえてまとめた廃炉に向けた「中長期ロードマップ」(廃炉工程表)を決定、公表している。これによれば、燃料取り出しは2021年内から開始し、30年~40年で廃炉を完了するのだという。にわかに信じることはできない超楽観的な見通しだ。ここで断言しよう、廃炉は今世紀中には完了しない。
燃料デブリの取り出しは、ロボットなどを使った遠隔操作に頼らざるをえないのだが、その技術は現在開発中である。ロボットによるトライアルは行われているが、現状では約880トンもある燃料デブリを、いわば耳かきで収集しようとしているものだ。取り出し技術がいつ実現するかは見通せないが、仮に実現して初号機で成功したとしよう。だが、同じ技術がそのまま他号機に適用できる保証はない。その場合、開発のやり直しになる。その繰り返しになる可能性もあり、不確定要素が山積みである。
廃炉作業は遅々として進まず、自ずとスケジュールは延び延びになるのは自明だ。つい先日ようやく3号機の使用済燃料の取り出しが終了したことからも容易に想像がつく。
また、まるで他人事のような原子力規制委員会更田豊志委員長の次の発言が裏打ちしている。
「(廃炉完了を)敷地に核燃料物質が残っていない状態を指すとするなら、行き先が決まらなければ出せない。多くの関係者の同意や理解が必要だ」
「今そうした議論を詰めることに意義があるとは思っていない。最終完了の時期をうんぬんするのはまだまだ先だ」
4.汚染水
汚染水の貯蔵量は、2月18日現在で約124万7000トンである。一般のドラム缶に換算すれば約620万本、皇居のお堀の水の約2.6倍ととてつもない量である。 国や東京電力は、海へ希釈・放出したいのが本音であろう。汚染水を「処理水」と言い換え、「風評被害」対策の検討とすることからも明らかだ。だが、もう地元の漁協組合等の了解を得れば良いという国内に限った問題ではない。もはや、海洋放出は国際問題と化しているのだ。
それにしても、なぜ海洋放出か大気放出の二者択一なのか。石油コンビナートにあるような大型タンクでの長期保管という選択肢もあるはずだ。希釈して30年をかけて海洋放出するのであれば、大型タンク貯蔵でトリチウムの減衰を待てばいい。希釈と言うのならば、逆に海で濃縮される可能性も考慮する必要もなくもない。事故後10年が経過しても漁獲されたクロソイから、国の基準を超える500ベクレル/kgの放射性セシウムが検出されたばかりだ。
東京電力は、貯蔵タンクの設置に限界が来ていると言うが、そんなことはない。敷地北側には7、8号機建設予定地があるし、敷地外にも広大な土地がある。
この問題で「たられば」は禁物かも知れないが、東京電力が初動をきちんとやっていれば。もともと地下水が多い敷地であることは、東京電力は重々承知していたはずである。にもかかわらず、原発担当の馬淵澄夫首相補佐官(当時)が提案した、地下遮水壁いわゆる地下ダムの建設に対し、東京電力が難色を示し、結局実現しなかった。その理由は、ダム建設に国が支払う保証のない1000億円がかかる。それが、東電の債務増と受け取られれば株価がまた下がり、株主総会を乗り切れない、という目に余るものだった。今そのツケが回ってきている。
なお、トリチウム水と純水とでは化学的特性は同一であるが、物理的には異なる(質量、氷点など)ことから、理論的には分離が可能である。再稼働のための安全対策工事に要する何兆円ものお金を汚染水の「無毒化(トリチウム除去)」研究開発に充当すれば、実験室規模はもちろん実機ベースでの実現も決して夢ではない。
5.再稼働ありきの新規制基準の策定
(1)世界一厳しい基準はウソ
そもそも発生頻度が一原子炉当たり100万年に1回程度で「工学的には起こり得ない」が通説だった炉心溶融事故が、実際に起きてしまった。しかも、同時に三つの原子炉で、である。その発生頻度は(100万年に1回)×3、と天文学的数字になる。これが何を意味するかといえば、「何が起きても不思議ではない」、つまり「何でもあり」の世界まで到達してしまったということである。だとすれば、これまでの安全設計思想(フィロソフィー)が正しかったのか。いちから検証しなければならない。つまり国際原子力機関(IAEA)の5層からなる「深層防護(Defense in Depth)」にまで踏み込む必要があったのではないか。もとより、日本の安全基準は米国とは異なり第5層(放射性物質が大量に放出された場合、放射線影響を緩和する=防災対策)はカバーしていなかった。
しかし、そのようなことは全く顧みることなく、新基準はわずか1年で策定された。相変わらず第5層は対象外、「安全基準」を「規制基準」と言い換えた。事故の原因さえ特定されておらず、教訓とする材料もないままだ。こんな新基準はあまりにも付け焼き刃的過ぎると言わざるを得ない。「対症療法基準」と呼んでいいだろう。どこが「世界一厳しい基準」なのか。片腹痛い。「コア・キャッチャー」や「二重格納容器」の設置を義務付けてはどうか。どう考えても再稼働ありきの基準であるのは論を俟(ま)たない。
(2)テロ対策は特重施設でお茶を濁す
福島第一原発事故は、原発の抱えるアキレス腱を露呈し、テロリストにとって格好のヒントを与えたと考えられる。原子力規制委員会は「テロ対策」にも踏み込んだとされるが、特定重大事故等対処施設(特重施設)を設置すること、それも「執行猶予」5年で、お茶を濁している。
これに関連して、
「原発が弾道ミサイルの攻撃を受けたら、どのぐらい放射性物質が出るのか」
と、山本太郎参議院議員(当時)が国会で質問した。これに対して、政府は「国民の生命・財産を守るため、平素より、弾道ミサイル発射を含むさまざまな事態を想定し、関係機関が連携して各種のシミュレーションや訓練を行っているところである」とした上で、「原発へのミサイル攻撃の事態は想定していない」とにべもない回答をした。結局「仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい」とする逃げ口上に行き着いてしまったようだ。
ここで、弾道ミサイルを発射するのは北朝鮮であり、テロの範疇を出るものかもしれないが、原発にミサイルが着弾したならば、壊滅的な被害が出るのは自明である。普通のミサイルが核弾頭(Dirty Bomb)と化してしまうのであるから、北朝鮮にその気があれば、お誂え向きの標的であろう。日本海及び東シナ海沿岸に撃ってくださいと言わんばかりに並んでいるのだから。それは、当然政府も理解しているはずである。
この国では、原発の「テロ対策」について包括的な規制基準になっていないどころか、法令上も体系的な整備がなされていないのが現状である。いかに危機感がなく、対策が脆弱であるかを痛感させられる。
(3)致命傷となった原発運転期間40年ルールの例外規定
原発事故による反原発の世論の高まりを受け、民主党政権(当時)は「脱原発」の象徴的な政策として、40年ルールを打ち出した。このために原子炉等規制法を改正したが、例外も規定し、運転開始から40年の時点で、将来の劣化に備えた対策が十分だと原子力規制委員会が判断すれば、最大20年の運転延長が可能とした。原発推進派への配慮によるものと考えられるが、これが現在骨抜き状態となり、老朽原発が再稼働できる根拠となっている。
コンクリート構築物の寿命は40年程度、が業界の通念であるが、原発の場合、原子炉圧力容器の中性子照射による脆性化(劣化)が寿命の目安となる。この脆性化度合い(脆性遷移温度の上昇)を判定するために、原子炉圧力容器内に複数の試験片が据え付けられている。試験片を分析しても理論上の脆性化傾向に合致することは、ほとんどないのが現実である。原子力規制委員会関係者も「原発の寿命の計算を詰めて議論するのは困難だ」と語っているほどだ。
したがって、40年ルールをなし崩しに変えるのは致命傷となる、本来の目的のとおり厳しく規定すべきと考える。
6.原発再稼働とエネルギー政策
(1)電力供給安定化、カーボンニュートラルを理由に再稼働
安倍前政権は、まるで福島第一原発事故などなかったかのように、「原子力規制委員会により新基準への適合性が確認された(その後「原子力規制委員会が安全と判断した」との表現で定着)原発については、その判断を尊重し再稼働を進める」とした。そして、福島第一原発とは型が異なるとでも言いたげに、PWRが再稼働を進めている。
その主な理由は、電力供給の安定化であるが欺瞞に過ぎない。世界の趨勢(すうせい)から見ても言わずもがなである。電力需給も地産地消の時代である。原発のよる大規模生産・大規模消費は時代錯誤であり、高度成長期を謳歌した人たちのノスタルジーで、どこか悲哀さえ感じる。
一方、菅政権はやみくもに「2050年カーボンニュートラル」を打ち出した。これも、原発必須の理由付けなのだろうが、それ以外の具体的な政策が見えない。無論、地球温暖化対策の重要性は認めるが、だから原発というのはいただけない。
ここで、気になるのは、脱原発を目指すはずの野党第一党立憲民主党の枝野幸男代表が、2月8日に西日本新聞の取材に応えた内容である。以下抜粋する。
「原発の使用済み核燃料の行き先を決めないことには、少なくとも原子力発電をやめると宣言することはできません。使用済み核燃料は、ごみではない約束で預かってもらっているものです。再利用する資源として預かってもらっているから、やめたとなったらその瞬間にごみになってしまう。この約束を破ってしまったら、政府が信用されなくなります。ごみの行き先を決めないと、やめるとは言えない。でも、どこも引き受けてくれないからすぐには決められない。原発をやめるということは簡単なことじゃない」
信じられない発言である。核燃料サイクルが破綻している現状では、使用済燃料はゴミでしかない。運転を続けたらそのゴミを増やすだけであるから、運転してはならないのではないか。本質をわきまえない詭弁というのも憚(はばか)られる。
(2)BWR急先鋒の東京電力の再稼働
財政事情からも再稼働したい東京電力の前のめりぶりは目を覆うばかりだ。原子炉設置変更申請が許可されたものの、原子力規制委員会に再稼働の適格性を厳しく指摘され、保安規定に「7つの約束」という精神論を記載するという異常な対応でようやく認可された。地元同意に大きく影響する柏崎市長・刈羽村長の改選を昨年クリアし、一気呵成(かせい)に再稼働へ突き進むはずの東京電力だったが、今年に入り躓(つまず)いた。内部通報によりIDカードを不正利用した中央制御室入室が公になった。その最中に行われた安全対策工事完了に伴う住民説明会実施期間中に工事未完了が発覚、説明会終了後も未完了が次々と明らかになった。これらにより、住民の東京電力に対する信頼感は地に堕ちた。
この問題は、参議院予算委員会でも取り上げられ、菅首相をして「極めて遺憾」と言わしめた。あとは、原子力規制委員会の判断待ちとなるが、東京電力の安全文化の欠如、コーポレート・ガバナンスの瓦解(がかい)が浮き彫りになったと言えよう。保安規定、核物質防護規定に抵触するのは間違いなく、再稼働の時期は新潟県知事の同意を前にして、先行きが見えなくなっている。
(3)原発依存であるが故にアップデートされないエネルギー政策
この冬の厳寒で年初電力が逼迫した。福島第一原発事故後、全54基の原発のうち再稼働したのは9基。特重施設設置の期限切れなどで、年初はわずか3基しか稼働していなかった。しかし、これが原因ではない。原発に依存するがあまりエネルギー政策を現実的なものにアップデートすることができない構造的な問題が根幹にある。
そこには電力自由化が大きく影響している側面もある。電力市場で他社との価格競争が激化し、燃料(液化天然ガス)や設備は余剰に持てないことや、原発再稼働に期待して、供給余力となる老朽火力発電所などを閉鎖したことも要因の一つとなっている。
第二次安倍晋三政権は、2014年策定のエネルギー基本計画で原発を基幹電源とする方針を定め、30年度時点の総発電量に占める原発の比率を20~22%とする目標を打ち出した。その一方で経産省は電力自由化を推進した。
だが注目すべきは、その後のエネルギー政策の膠着状態だ。目標とする原発比率を実現するためには30基程度の稼働が必要にもかかわらず、再稼働したのはわずか9基である。にもかかわらず安倍政権は原発の新増設を指向した。2018年の計画改定の際には、議論もないまま世耕弘成経産相(当時)が「基本的には骨格を変えることはない」と宣言した。有識者からは「行政は不都合な現実から目を背けている」と不満の声が漏れたという。
この改定では、再生可能エネルギーを主力電源とする方針が示されたものの、政府は昨年6月、国民負担の増加を理由に再エネの普及を後押ししてきた固定価格買い取り制度(FIT)を市場連動型へと抜本的に見直すことを決めるなど、どっちつかずの状況が続いている。このような政策の軸が定まっていない状況では、再エネも推進するのかしないのか電力会社が当惑するのは当然だ。そして、今回の電力逼迫が露わになった。
早急に原発依存から脱却し、確固たるエネルギー政策を掲げ、電力会社に設備投資のインセンティブを与え、健全な電力市場を保つことが電力供給の安定化にとって必須事項ではないだろうか。(了)