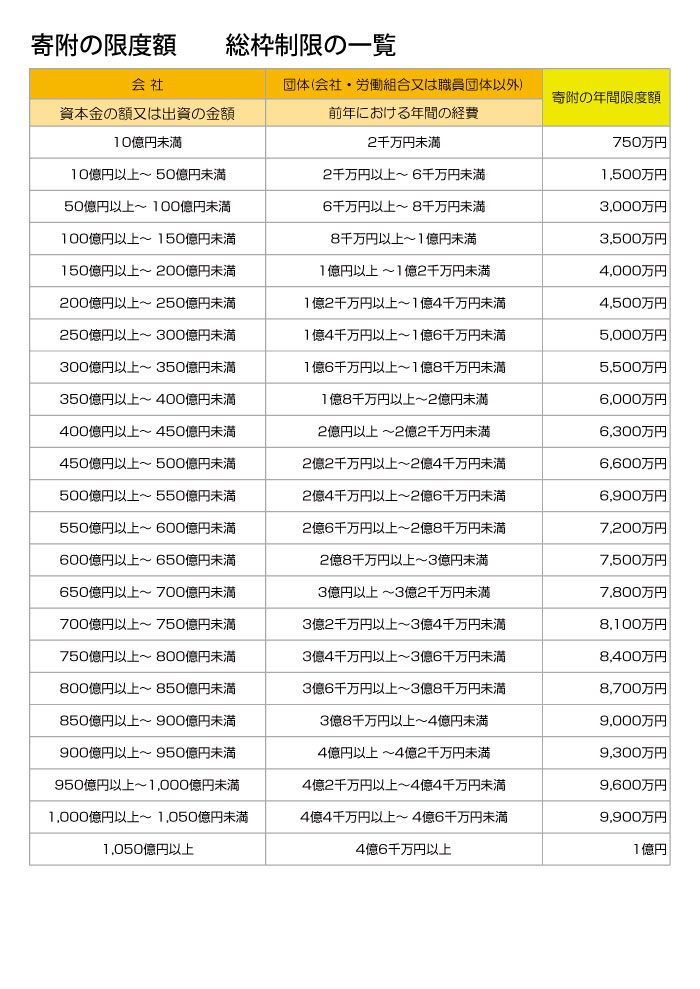1947年5月3日、つまり78年前の今日、日本国憲法が施行された。
この憲法の理念を守り、実現していくために、
我々国会議員はなすべき議論を尽くしてきたのか、反省を込めて考えたい。
国会において憲法について議論される場が「憲法審査会」だ。
その役割は2つある。参議院のサイトには、
(1)日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調査、
(2)憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等の審査、
となっている。日本国憲法に関する総合的調査を第一の目的にしている点が重要だ。
ところが、この数年間の憲法審査会、特に衆議院においては、
改憲5会派(自民、公明、維新、国民、有志の会5会派)を中心に
日本国憲法がしっかり実現されているかチェックする「総合的な調査」をそっちのけに、
声だけは大きい改憲派たちにより、今の憲法を早く変えることの
議論ばかりがなされている。
彼らが現在最も力を入れているのが、「国会議員の任期延長のための憲法改正」だ。
あからさまな緊急事態条項の創設をいう事は反発が大きいので、
ただ「包み紙」を変えたわけだ。
議員任期の延長改憲とは、
4事態(➀災害、②テロ・内乱、③感染症、④国家有事・安全保障)と
それに匹敵する事態で、内閣・国会の判断で任期満了や衆院解散によって
失うことになる衆議院議員の身分を延長(復活)させるものが主として想定されている。
このような事態には国政選挙が実施できないので、国会議員の任期を延長しないと
緊急事態に国会が機能しなくなる、というのが彼らの主張である。
しかし、大災害等の国の緊急事態への対処条項は
すでに日本国憲法にはすでに存在している。
それが憲法54条に規定がある「参議院の緊急集会」の規定だ。
○憲法54条
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
この54条は、衆議院議員が解散や任期満了でその職を失ったときでも、
参議院において緊急集会を招集し、次の国会開会までの間、
国会の役割を果たすことを決めているものだ。
戦前、1941年に1年間の任期延長が行われ、その下で戦争遂行の国内体制整備が進んだ。その反省から、緊急時にあってもその権力乱用の危険を排除し、
国民の自由と権利を守り抜くものとして緊急集会の規定が制定された。
だから、「任期延長改憲論」は日本国憲法の制定過程の議論も無視した「暴論」なのだ。
■改憲派の任期延長改憲論は既にオワコン
改憲派の方々は、「緊急事態条項」や「議員の任期延長」を必要とする理由として、
参議院の緊急集会には欠陥があると言う。
「緊急集会は平時の制度だ」とか
「緊急集会で対応できるのは70日間だけだ」という議論だ。
これらの論点は参議院の憲法審査会においてしっかり否定されているし、
実は、当の自民党自身が昨年、議論の末に意見を取りまとめ、否定している。
現に、自民党・憲法改正実現本部の
ワーキングチームとりまとめ(2024年8月7日)では、以下のように書かれている。
〇「参院の緊急集会」が緊急事態に対応するための唯一の緊急事態条項であり、参院の重要な権能である
〇緊急集会の期間について「70日間は、厳格に限定するものではない」
〇「緊急集会の権能については、(略)原則として『国会の権能の全て』に及ぶ」(注)
(注)憲法改正実現本部ワーキングチームが議論の取りまとめを報告 | ニュース | 自由民主党 憲法改正実現本部 (2024年8月7日)
この見解は、引き続き、今年の参議院憲法審査会でも自民党側の幹事が確認している。
いわば衆議院側の暴論ともいえる改憲論を参議院側の正論が否定した形となり、
議論の結果、党の見解は参議院側の見解が採用されたのだ。
要するに、任期延長改憲論は、自民党内でも既に「詰んで」いるのだ。
これを維新などの改憲派が「壊れたレコード」のように繰り返している。
任期延長ではなく、緊急時であっても国民の選挙権はしっかりと保障されるべきだ。
日本全体で選挙が実行できないという事態は想定しにくく、
部分的にも選挙を実施していけばいいだけの話だ。
国会で本来議論すべきは、任期切れの議員を「ゾンビ」として復活できるような
改憲議論ではなく、緊急時においても速やかに民意を反映した投開票ができるように
万全を期す選挙制度改革、法整備の議論である。
■憲法をどう変えるではなく、憲法をどう実現するかを議論すべき
憲法審査会を開くなら、最優先は調査。現行の憲法と密接に関連する法制度が
憲法の趣旨に沿って運用されているのか、憲法の趣旨に則してどのような
法改正が必要になるのかを議論し、政府に突き付けることだ。
なぜなら、憲法の趣旨とは180度違う棄民政策とも言える
国家運営が行われ続けているのが日本国なのだから。
○憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
○憲法25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
先進国で唯一、30年も経済不況が続くも、国を切り売り、民を切り捨て、
今や国民の6人に1人が貧困。貧困家庭にとどまらず、
国民全体でも約6割が生活が苦しいという状態で、中間層も追い込まれている。
現政権の構成員達は国民の生存権に興味もなく、
全体の奉仕者である公務員としての役割も放棄。
経済的に追い詰められた国民にとって最後の命のとりでが生活保護。
自民党は、生きるか死ぬかぎりぎりの状態にある人でも、
保護の利用をためらう恥の概念を埋め込んだ。
自民党の強行した生活保護引き下げ。
この非人道的引下げを憲法25条違反などで訴える「いのちのとりで裁判」では、
受給者側の訴えを認める高裁判決が続く。
本来、このような生活保障の問題こそ、衆参の憲法審査会で取り上げ、
最高裁判決を待たず、会として決議を出し、
憲法に則した生活保護費の支給を政府に求めるべき案件ではないか。
衆参憲法審査会が2007年に設置されてから、この憲法13条や憲法25条に特化した
テーマ設定で調査が行われた回数はゼロ回。
今、憲法について行うべき議論は、失われた30年の経済・労働政策が
いかに憲法が保障する人権を破壊してきたか。
国民生活を底上げして、失われた30年を取り戻し、
ジャパン・アズ・ナンバーワンを、日本を再興するための
最後のとりでが日本国憲法。本質的な議論を行うべきだ。
2025年5月3日
れいわ新選組